2022年7月2日の早朝よりauの回線で通信障害が発生し、7月3日には西日本や東日本地域での復旧作業を実施したとの報道がなされました。しかし、通信の問題自体はその後も続き、記事執筆時点の7月5日では完全復旧は7月5日の夕刻を目処に発表される予定だとの報道がなされている状況です。
7月2日の朝から通信ができなくなったことに気づく
7月4日の午後まで私のau回線のIIJmioのSIMカードも通信ができませんでした。障害自体の復旧作業は7月3日の午後には作業が完了したとの報道がなされていましたが、私の住んでる地域では実際に通信が可能になったのは7月4日の夕方でした。
私が持っているau系のsimカードはIIJmioのSIMです。契約するときにドコモ、au、ソフトバンクの中から好きなキャリアを選べたため、その時にはドコモ系の格安SIMを他に1枚持っていたし、会社から支給されている電話はソフトバンクでしたのでリスクを分散させるためにもauを選択しました。
7月2日は早朝からジムで筋トレを実施してから仕事場に向かいました。私の生活のサイクルは早朝にジムで筋トレを済ませてから仕事に行くという流れです。起床時刻は3:00ちょっと前。障害が発生したとされている時刻が1:35分頃とされていますのでその時点で既に通信障害は発生していたはずですがIIJmioのSIMカードを挿入しているPixel 6 Proはサブ端末でしたのでジムに着くまでは使えないということに気付きませんでした。
ジムで筋トレ中にようやくよく見るとアンテナピクトが立っていない事に気づきました。私は通信は全てUQ Wimaxのモバイルルーターに流して通信しています。常に持ち歩く端末はメイン端末のiPhone 13 Pro Max、サブ端末のPixel 6 Pro、iPad Pro 11インチ、Macbook Pro 14インチ、Kindle Paper White Signiture Editionです。これら5台の端末全てがGalaxy 5G Mobile Wi-Fiに接続して通信するという形にしています。
UQのWimax自体は通信できていたため、データ通信は使える状況でした。通話自体は会社用のソフトバンクのSIMカードで、プライベートの通話自体はほぼありませんが楽天モバイルのSIMを刺したiPhone 13 Pro Maxで使うので全く影響がありませんでした。Pixel 6 Proのアンテナピクトが立っていない事に気付いた時にはIIJmioの支払いに使っているクレジットカードが更新されているのに支払い情報を更新していなかったために支払いができず通信停止処分を食らったのではないか?と最初に疑いました。急いでマイページから支払い情報を見ると問題なく決済できており、ニュースを見てみると通信障害が発生しているとのことでようやく通信障害の発生自体に気付いたという流れでした。
複数SIM、複数端末は最強の冗長化
冗長化という言葉がネットワーク業界では昔から使われていました。冗長化とはシステム障害に備えてサーバーや通信回線などを一つで運用するのではなく複数で運用してどれかに障害発生した時に他のサーバーや通信回線を使用して障害を回避するという考え方です。私がこの考え方を知ったのは中学生の頃に自分でウェブサーバーなどを運用しようとしていた時のことです。
当時は2000年代初頭で現在とは比べ物にならないほど通信回線の維持費やサーバーの費用がかかる時代でした。子供の私にはとてもそんな費用は払えるはずもありませんでしたが、商用のシステムを運用するのであればそういった費用は必要経費なのだなと思った記憶があります。
それから約20年経過して大人になった今もIT関連への興味は継続していて、SIMカードは3回線、端末も複数と自然に冗長化している状況でした。またSIMカードを選ぶ時も価格はもちろんですが、価格がほぼ変わらないのであれば通信キャリアを複数にばらけさせる様にしたりといったリスク分散の考え方を身に付けたのは中学生の時に学んだ冗長化という考え方からでした。
もちろん普通の人が私のようにたくさんの端末やSIMカードを持ち歩くような世界が来るとは思えませんが、この20年で確実に良くなったのは通信回線のコストが劇的に下がったことです。データ通信専用でよければ月額500円程度で1回線が維持可能です。普通の人間でも障害に備えて普段は物理SIMカードでメイン回線を使用しながらeSIMで2回線目を契約しておく、などの使い方がかなりの低コストで実現可能になりました。
あらゆる情報がインターネットを媒介としてやりとりされる現代社会では通信インフラはもはや最も重要なインフラの一つと言えます。通信障害が発生するとたちまち仕事やプライベートの連絡で多大な影響を及ぼします。IoTが普及しており、場合によっては家の鍵が開かないなどの問題が発生することだって考えられます。
eSIMは開通まで即日で1時間程度で開通可能なことも
eSIMとは組み込み式のSIMカードで、対応した端末の内部に利用者が契約した契約情報(SIM)を書き込んで使うという方式のことです。物理的なSIMカードをなくして端末内部に埋めんで使うというイメージでしょうか。
eSIMのメリットは物理的なSIMカードを使用しないため、コストを抑えることができたり(事務手数料が安い場合が多い)、契約してから回線が開通するまでの時間が短くなったり、キャリアによりますがeSIM専用の安価なプランがあったりします。
一方で対応した端末でないと使えず、しかも最近出てきた規格のため対応端末が少ない、対応キャリアでないと使えない、物理的なSIMカードではないので端末間のSIMカードの移動がキャリアのサイトから手続きをしないといけないなどの手間が増えるなどがあります。
障害が発生してある程度(半日から1日以上)長期化する場合には、障害発生後にeSIMで契約するといった使い方も考えられます。例えばahamoであれば契約申請後に開通まで最短で1時間程度で開通可能です。物理的なSIMカードを郵送する必要がないからこそのメリットですね。
通信障害などのリスクについて普段から考えておこう
一つの端末で一つのSIMカードで運用するのが最もコスト的に考えれば安価です。それは間違い無いでしょう。しかし、その安い価格にはそれなりのリスクを受け入れるからこその価格であることを忘れてはいけないと思います。
障害を起こしたこと自体は誉められたことではありません。通信障害を起こしたことを責めるのも簡単です。でも通信障害が発生した損害は誰も保障してくれません。通信障害が起きた時に発生した機会損失などは全てお金で補償できるものでしょうか。お金で解決できない問題もたくさんあるはずです。そういったことまで全て通信事業者に責任を負わせるのであればそれ相応のコストを利用者は覚悟しなければいけないと思います。リスクと価格は反比例するトレードオフの関係です。
昔から通信サービスではベストエフォート型サービス(通信速度の保証はしない代わりに価格が安い)といった考え方がコンシューマ向けでは主流です。最低通信速度が保障される帯域保証型は会社などで使われる契約で、価格がかなり高いです。リスクをどこまで受け入れるかどうかで価格が変わるんですね。
一つのSIMカードを利用するということは基本的に一つのネットワークに依存するということを意味しています。そのネットワークに何かがあったら回避手段がないというリスクが潜んでいるわけです。そのリスクを回避するための最低価格はいくらでしょうか?
IIJmioのeSIM専用サービスであるデータプランゼロは月に1GBまでの通信で月額495円です。欠点はドコモのネットワークしか選択できないことです。すでにドコモのネットワークがメインである場合にはリスク回避といった目的では選択肢から外れるでしょう。
ドコモやソフトバンクがメイン回線である場合にはpovo2.0は有力な選択肢だと思います。povo2.0であれば基本量は月額0円で、必要な時に必要な分だけのデータ通信量などをトッピングから選択して購入することができます。auユーザー以外であればpovo2.0が最高のコストパフォーマンスを誇る選択肢であると思います。
昔に比べてネットワークのコストは劇的に低下し、さらに選択肢は格段に増えました。今回のネットワーク障害は普段から自分がネットワークに対して払っているコストとリスクについて考える良いきっかけになったのでは無いかと思います。
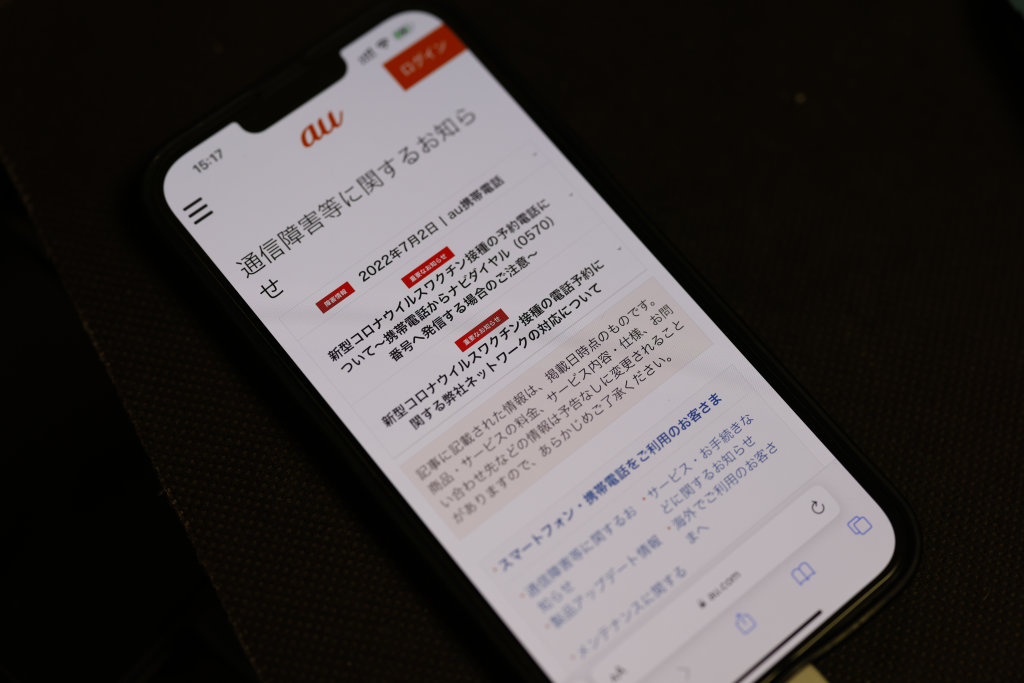
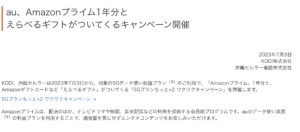
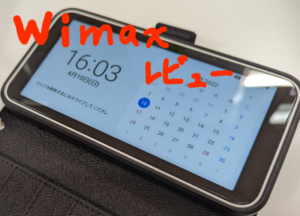


コメント