私は現在看護小規模多機能型居宅介護施設に併設された訪問看護ステーションで訪問看護の仕事をしています。看多機のデイサービスを利用している利用者を対象にしたデイサービスでの看護、看多機利用者の訪問看護、訪問看護ステーションでの訪問看護を主に担当しています。
この記事では看護師の視点から見たパーキンソン病について私が調べたり経験したりしたことを記事にしています。この記事の対象者はパーキンソン病について知りたい・パーキンソン病の人と関わっている介護士の方でパーキンソン病を知りたい・パーキンソン病の看護・訪問看護について知りたいという方に向けて書いています。
パーキンソン病は脳の黒質の細胞が変性してドーパミンの分泌量が低下することによって体の動作が悪くなってADLが低下していく病気のことです。
主に発症しやすいのは50歳以降で、日本では約15万人の患者さんがいると言われています。1000人に1人ぐらいいる計算になります。ちなみに65歳以上に限定すると100人に1人くらいいます。100人に1人だと統合失調症の患者さんと同じくらいの確率ですね。
症状として大きく分類すると体の動作がスムーズに動かなくなる運動障害と、自律神経がうまく働かないことによる自律神経障害に分類されます。
治療の中心は薬物療法で、場合によっては脳深部刺激療法(DBS)と言われる手術療法が行われることもあります。
運動障害
運動障害の症状は大きく4つあります。
- 安静時振戦
- 無動
- 筋強剛
- 姿勢反射障害
- (無動と姿勢反射障害の結果としての)歩行障害
体を動かしていない時に手や足が震えることを言います。体を動かしている時には震えが止まります。パーキンソン病の初期症状として出ることが多いです。
手が震えることによって内服薬の袋を開けて手に取って口まで運び、コップの水を飲むという一連の動作がしにくくなります。場合によっては内服薬を一部落としてしまうこともあるでしょう。飲みやすくするためにはどうすれば良いでしょうか。内服は一包化されているでしょうか。内服は取りやすい場所に保管されているでしょうか。コップは持ちやすい形状ですか。
箸が持ちにくいのであれば介護用の持ちやすい箸を検討できます。スプーンを利用したり持ちやすくする工夫が考えられます。字が書きにくい場合には音声入力を利用できるスマホを利用するなど代替手段を考えてみましょう。
体がほとんど動かせなくなったり、動作の速度が遅くなったりする症状です。体の動きが制限されることで具体的には表情が乏しくなる仮面用顔貌、声が小さくなる、小さい字しか書けなくなる小字症などの症状となって日常生活に影響が出ます。
朝起きてから着替えるのに時間がかかったり、入浴前後の着替えで時間がかかることがあります。デイサービス中のお風呂の場合、着替えに時間がかかるのであればあらかじめ早めに浴室に連れていったり、入浴の順番を工夫したりできるかもしれません。
仮面用顔貌の症状が出ると表情が非常に乏しくなります。人間は言語以外でも表情や体の動きといったボディランゲージからも情報を読み取っています。また声も小さくなりがちですので聞き取りにくいといった問題も出てきます。パーキンソン病の方とのコミュニケーションを取る時にはそういった情報が読み取りにくいということを認識した上で関わっていく必要があります。
筋強剛とは筋の緊張が強くなってしまい、筋肉の収縮と弛緩のバランスが崩れてしまい関節が固まったような状態になってしまうことを言います。腕を伸ばしている状態から曲げた状態に持っていく時に筋肉がうまく動かなくて曲げにくくなるなどの状態になります。本人は自覚しにくい症状ですが、体の動きがぎこちなくなります。
人間は体の位置がずれると無意識にバランスをとるようになっていますが、バランスを取ることが困難になり姿勢を立て直すことが難しくなることを言います。
パーキンソン病の方は特有の前傾姿勢になってしまいます。背中が前方に曲がり、横から見ると首から頭にかけて前に突き出したような姿勢になってしまいます。
バランスが一旦崩れると立て直すことが難しくなるので、歩き始めて状態が前のめりになると加速していって止めることができなくなる突進現象といった症状や後ろにバランスが崩れるとそのまま倒れてしまうなどの症状がでます。
突進現象や後ろにバランスを崩してしまった場合にそのまま倒れてしまいやすい状態ですので転倒リスクが高いです。突進現象の対策には杖を使用する、歩行器を使用するなどの歩行のバランスをとりやすい補助具の利用が検討できるでしょう。部屋の中などは転倒しやすい場所に手すりを設置するなどの対策が考えられます。また部屋の中でその人が必要とする道具(眼鏡、杖、薬、テレビのリモコン等)がベッドなど生活の中心となる場所の近くに配置されているかどうかなども検討できると思います。
無動や姿勢反射障害の結果、歩行しにくくなります。足を前に出すことができなくなるすくみ足や、足の裏が床からほとんど浮かずに歩くすり足歩行・小刻み歩行、姿勢反射障害のところで解説した突進現象などが発生します。
歩きにくさに対する対策として歩幅に合わせて床にテープを貼って視覚的にリズム・刺激を与えてあげると歩きやすくなったり、足を動かすタイミングに合わせて手拍子を叩いてあげると歩きやすくなるなどの特徴があります。
姿勢反射障害のところでも説明していますが、転倒対策として歩行器や杖の使用・手すりの設置などが有効です。まだ使用していない場合には使用の検討をしてみると良いと思います。
非運動性症状
運動障害以外の非運動性症状には自律神経の働きがうまくいかなくなることによる症状、抑うつ・認知症などの精神症状などがあります。
自律神経症状
自律神経症状の発生機序についてははっきりとはわかっていないですが、パーキンソン病の方は迷走神経背側核にレビー小体が集まっていることが確認されています。レビー小体が集まると神経の伝達が阻害されます。その結果自律神経症状が発生しているのではないかと言われています。
- 便秘
- 排尿障害
- 血圧低下
- 発汗障害
自律神経は消化管を含む内臓の動きをコントロールしています。自律神経がうまく働かなくなることで消化管の動きが悪くなり、便秘になることがあります。
また、治療薬として抗コリン薬(トリヘキシフェニジル、ビペリデン、ピロヘプチン、プロフェナミン)を使用することがありますがこれらがアセチルコリンの受容体の働きを弱めることによって副交感神経優位になりにくくなり消化管の働きが悪くなるということがあります。
また運動障害が発生することにより手の巧緻性が低下して食事に時間がかかる結果食事量が減る、体が動かしにくくなるので運動量が減り食欲が低下して食事量が減る、そもそも体が動かしにくいのでトイレになるべく行きたくなくなるのでトイレを我慢して便秘になっているなどの可能性もあります。
トイレに行くのが大変で排便を我慢している場合、恥ずかしくて周りの人に相談できない可能性があります。定期的なトイレ誘導、ポータブルトイレの利用、トイレまでの導線で歩きやすくする工夫(手すりの設置、邪魔なものを掃除する)など援助できることがあるかもしれません。
手の巧緻性が低下した結果、箸が持ちにくくて食事に時間がかかって食事摂取量が低下している可能性があります。食べやすいもの(お米ではなく手で食べられるパンにする)を選んだり、箸ではなくスプーンを使用する・介護用の箸を利用するなどの対策が検討できるかもしれません。
便秘がある場合には下剤の処方がある場合がほとんどだと思います。下剤の使用量が適切でしょうか?排便パターンについて最も確認しやすいのは普段から接している介護士・看護師だと思います。下剤の使用と排便パターンについて記録をしていき、主治医に報告して処方内容について改善が検討できるのであれば検討してもらうなどの対策ができると思います。
夜間にトイレに頻回に行く(頻尿)、我慢できないほどおしっこに行きたくなる感じがする(尿意切迫感)などの症状が出ます。失禁してしまう場合もあります。
排尿・排便の失敗は羞恥心を呼び起こします。失禁してしまった場合、それを家族や友人、介護士や看護師にすぐに相談できるでしょうか。自分が失禁したということを隠そうとするかもしれません。また場合によっては主介護者である家族から叱られてしまうケースもあるかもしれません。恥ずかしい、失敗したくないという気持ちを強く持ってしまうとトイレを我慢するかもしれません。失禁についてお話を聞く場合には周りの人に聞かれない場所で聞くなどの配慮を忘れないようにしたいです。
夜間に頻回にトイレに行く場合、夜ちゃんと眠れない可能性があります。その場合は日中に眠くなってしまい、覚醒レベルが低下して転倒につながるという可能性も考えられます。夜寝る前にトイレ誘導をする、夜トイレに行きやすいようにポータブルトイレを利用するなどの対策などが検討できると思います。
立ち上がってから3分程度以内に血圧が低下することを起立性低血圧といい、食事性低血圧は食事後に腸管に血液が集まることによってその他の場所の血流が減少した結果に生じる血圧低下のことを言います。
血圧低下の症状としてはめまいがする、気分が悪くなる、意識レベルが低下する、吐き気・嘔吐、倦怠感・疲労感などが出現します。
ベッドで横になっている状態から立ち上がるのであれば一旦ベッド上で端座位になってもらい落ち着いてから立ち上がってもらう、症状が出現したら横になってもらう、足を挙上するなどの対策が考えられます。
食事中に血圧低下の症状が出現し、実際に血圧も低下しているのであればベッド上で食べてもらうなどの対策が考えられます。また吐き気を訴えているのであれば嘔吐物で窒息しないように姿勢を整えるなどの工夫もできるでしょう。
自律神経の機能が低下することや、体温調節中枢がある視床下部の神経の機能が低下することによって発生すると考えられているが原因は詳しくはわかっていないです。
多くの場合は体幹などで発汗が減少し、逆に顔面などに発汗が増えるといった症状であることが多いようです。
顔面に発汗が多い場合には顔面清拭を実施するなどして清潔を保つ、うつ熱が認められる場合(かなり稀なようです)には室温の調節や掛け物の調整などを実施するなどの対応ができると思います。発汗が多いのであれば水分摂取も大切です。
精神症状
精神症状には認知症による認知機能低下、不眠、うつ症状、幻覚、幻聴などがあります。
パーキンソン病の発症から時間が経てば経つほど認知症の併発率が上昇する傾向があり、パーキンソン病と認知症状の高い関連性があります。
認知機能低下による内服忘れが起こると、ほとんどのパーキンソン病の方に処方されている運動障害に対する薬が飲めなくなってしまいます。そうすると運動障害が起こりADLが低下するという可能性が考えられます。内服を忘れにくい場所に置く(内服カレンダーの使用、起床時薬があるのであればベッド横にセッティングする等)、内服確認のための訪問介護を入れる、デイサービスの送迎の際に内服介助を実施する、内服しやすいように一包化を依頼するなどが考えられます。
適度な運動が認知機能低下と関連があるとされています。訪問看護で転倒に注意しながら散歩を実施する、デイサービスを利用している際に運動を実施するなど体を動かせるような関わりをすることができると思います。また頭を使うような脳トレを実施するなどの関わりもできるでしょう。
まとめ
病態と症状を解説するだけでかなり長くなってしまいました。
まとめるのが大変ですのでいくつかに分けて記事を書いていこうと思います。この記事を読んでパーキンソン病の方との良い関わりを持てるようになってもらえる人が増えたら嬉しいです。
長文を読んでいただきありがとうございます。
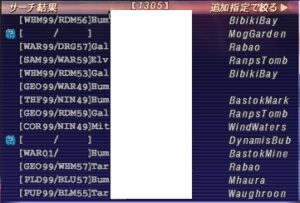
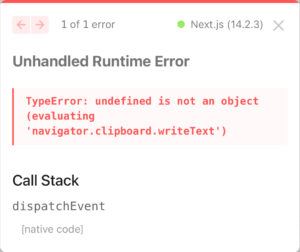
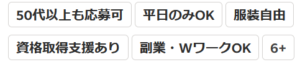



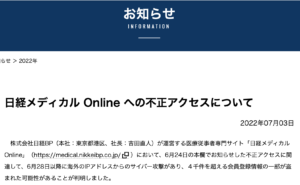

コメント